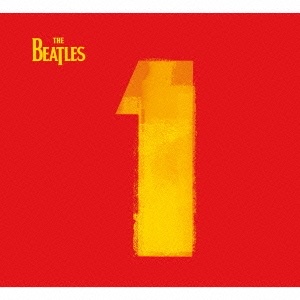2024年1月24日、ビリー・ジョエル16年ぶりの日本公演に行ってきた。
東京ドームでの一夜限りの公演ということでも話題だったが、これが最後の日本公演かも、という触れ込みもメディアを踊ったのはいつものこと。
ライヴの感想を先に言ってしまうと、すごくよかった。
長年のファンとして思い入れがあることも含むけれど、演奏、ヴォーカルの力強さなど、まだまだビリーは終わらないというのが印象に残った。
少し痩せたビリーはパフォーマンスが若返ったように思え、本人も前より楽しそうな感じがした。
それはやっぱり動きやすくなったり、声が出やすくなったり、軽くなったことから生まれた結果なのだろう。
集まった観客はわたしとおなじような長年のファンから、はじめてビリーを観るのであろう若い人まで幅広い。
そして男女比も偏っていないように感じた。
一夜限りの公演とは言え、ここまで広い層をドームで集めるのは、ポール・マッカートニーとビリーくらいだろう。
開演前、ドームは期待感が増していき、ビリーが登場すると爆発的な盛り上がり!
その空気は冷めることもダレることもなく、終演まで突っ走った。
なんだかこれからのビリーが楽しみになった。
そんな今後につながる期待感が残るライヴだった。
幸福感にあふれ、エンジンうなりまくりのロックンロール・ショウだったのだ。
ライヴ中に、来てよかった・・・!と素直に思えた。
最近そんな感情になるライヴがなかったから、わたしにとって心に残るショウとなった。
そんなビリーがひさしぶりの新曲を発表した。
TURN THE LIGHTS BACK ONである。
いまのところデジタルとアナログだけのリリースだが、おそらくCDリリースも発表されるのだろう。
追記:2024 3月 CDシングルでのリリースが決定した。
歌詞の内容から、ポップミュージック制作を引退した自身への悔恨を含んでいるようにも思えるし、ファンへのメッセージとも取れる。
なによりそのタイトルだ。
もう一度、レコーディング活動をはじめるということなのか!?
ビリーのホームページには新曲の紹介ページがあるが、そこには「ビリーは新章に向かう」といった旨の文章が添えられている。
またポップミュージックの制作をするのか、それともレコーディングはしないけれどライヴで披露していくのか。
いずれにせよ、期待感の余韻が残る中でのこのインフォメーションはビリーがなんらかの形で新曲を、それもポップミュージックにおける新曲を手がけるというニュアンスにしか受け取ることができない。
そこで今回の新曲をあらためて聴いてみる。
一聴してすぐに感じるのは、SHE’S ALWAYS A WOMANを想起するクラシカルなバラードであること。
ただバックに入ってくるリズムセクションはロックバンド然としたもので、このあたりはSHE’S ALWAYS A WOMANとは異なる点。
クラシカルなロッカバラードとして、2000YEARSのほうに近いようにおもう。
従来のビリー・ジョエルの作風を踏襲しながらもこれこそがワン・アンド・オンリーなビリーのスタイルであることを示しているのは意図的なものだろう。
その中でサウンドは現代的なものにしてあり、ヴォーカルのサウンドも現代的なものにしている感がある。
にしてもビリーの声が若い!
最初聴いたときはビリーが曲を提供し、若いシンガーが歌っているのかと錯覚した。
さすがにこれはヴォーカルソフトに通して多少は調整しているようにおもえる。
ただし、ビリーのヴォーカルは以前よりも素直な発声に戻っているのは数年前から。
93年頃から澄んだ声で歌わなくなったビリーのことを、もう昔みたいな綺麗な声は出なくなったとか、酒焼けした声と言っていたひとも多かったが、あれは意図的な発声。
澄んだ声を出そうと思えば今でも出せるのはジミー・ウェッブのトリビュートアルバムに提供したウィチタ・ラインマンに記録されている。
そしてそれは今回の日本公演でも証明されていた。
新曲TURN THE LIGHTS BACK ONでは、明らかにこれもまた意図して若かりし頃の声を聴かせている。
ソフトに通しているとしても驚異的な声の若さである。
結果、コンテンポラリーに偏りすぎないバランス感覚が光る仕上がりだ。
メロディも親しみやすく、盛り上がるパートもはっきりしており、メリハリが効いた楽曲。
プロデュースはフレディ・ウェクスラー。
曲はウェクスラー、アーサー・ベイコン、ウェイン・ヘクターとビリーが共作している。
ビリーが共作という形を取るのは珍しいが、
そうした形を取る許容ができるようになったこと、それによって新たな手応えを感じたのではないか。
他人と楽曲を紡ぐ楽しさと分かち合う喜びにビリーのインスピレーションが反応しているのだと思いたい。
インタビューではアルバムRIVER OF DREAMSはいい曲がたくさんあったのに、評判はいまひとつで、自身が置き去りにされてしまった感を覚えたとコメントしていた。
ポップミュージック制作からの引退にはいくつも理由はあるのだろうが、この置き去りにされた感というのは重い。
ビリーほどのスターだからこそ感じるものなのかもしれない。
だが、ようやくその冷え冷えとした感覚を打ち消してくれる作曲チームを組むことができたということか。
ひとりで抱え込まなくてもいいのだ。
そして、こうしたロック、ポップの範疇に入る曲を仕上げたのではないかと推測するのだが、やはりポップミュージックの制作再開を意味する、その序章に読める。
近いうちに久しぶりのアルバムを発表するに思えて仕方がない。
それほど今回のビリーのライヴは次を予見させる期待感を残していったのだ。
この感覚はデヴィッド・ボウイが長い隠遁を経て突如新作をリリースした驚きと歓喜が世界中を駆け抜けたあのときと似ている。
ワクワクする気分が溢れてくる。
ビリーのNEXT DAYを待ちたい。
上に追記したけれど、そんなビリーの新曲TURN THE LIGHTS BACK ONがシングルCDでリリースすることが決定!

TURN THE LIGHTS BACK ON シングルCD
画像クリックでHMVの商品ページが開きます。
これぞビリー・ジョエルな作風を見せた麗しのバラードだ。
70年代のビリー、特にストレンジャーからニューユーク52番街の頃を彷彿とさせる1曲。
ジャケットの戻ってきた感もいい。こちらはさまざまな年代におけるビリーの名曲をライヴテイクで聴くライヴ・ベスト。
元は2019年にデジタルのみでリリースされていた20曲入りのライヴ集。
それを日本独自編纂という形で、リプロデュースした32曲の2枚組CDだ。
その割に良心的な値段なのも嬉しい。
デジタル版とは収録曲の違いや、曲が同じでも収められたテイクが異なっているなどの変化がつけられているので、デジタル版をすでに聴いているひとも忘れずに持っておきたい。
ビリーのエネルギッシュなライヴを楽しめるライヴテイク集だ。
はじめてビリー・ジョエルを聴くひとはベスト盤と、このライヴベストを聴いてみるのもいい選択だ。
おわり